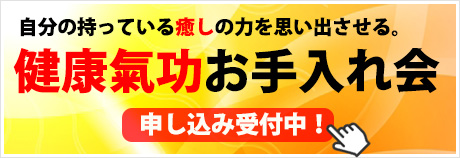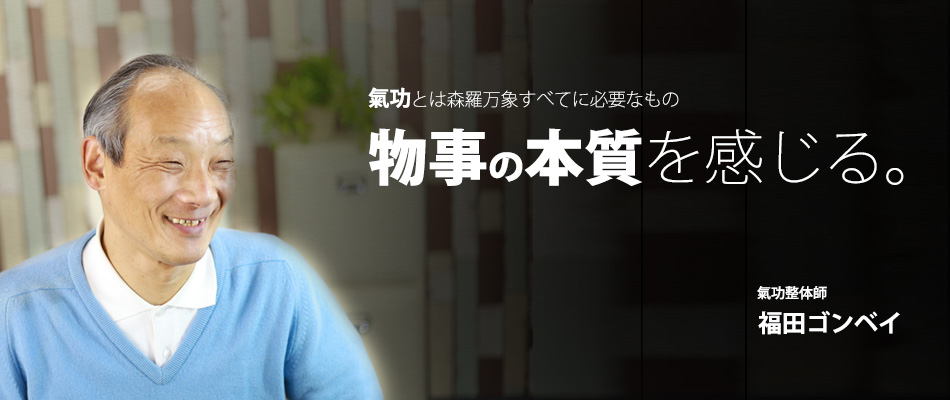
福田ゴンベイの「気功との出会い」
気功との出会い 〜福田ゴンベイ式気功メソッドの誕生〜
気功整体師への転身 〜妻の病気がきっかけ〜
私が気功整体師としての道を歩み始めたきっかけは、妻の病気でした。
それまで私は、やりがいのある仕事に打ち込みながら、健康で幸せな家庭にも恵まれていました。しかし、少しずつそのバランスが崩れ、仕事と家庭の両面で大きな試練に直面しました。そんなとき、妻の病気を治す手立てとして、そして経済的な新たな道を模索する中で、気功に出会いました。この出会いが、私の人生を大きく変えることになったのです。
福田ゴンベイ式気功メソッドの確立
身体と心の健康の関係
人間の身体は、日々の生活の中で蓄積される疲労やストレスによって血液やリンパの循環が滞ることで、不調を引き起こします。身体の疲れが抜けない状態が続くと、やがて心にも影響を与え、本来自分が持っている能力や意欲を十分に発揮できなくなります。そして、そのもどかしさがさらなるストレスを生み、負のスパイラルへと陥ってしまうのです。
身体が整えば、心も整う
本来の健康を取り戻すことで、心も軽くなり、自然と前向きな気持ちが生まれます。肉体と精神のバランスが整うことで、自信が生まれ、エネルギッシュに活動できるようになるのです。それにより、家族や職場など、周囲の人との人間関係もより良いものへと変わっていきます。
福田ゴンベイ式気功整体メソッドとは?
福田ゴンベイ式気功整体メソッド(別称:福翁氣光整体(ふくおうきこうせいたい))は、肉体と精神の健康を取り戻し、本来の自分の理想的な状態へと導くセルフケア法です。このメソッドを通じて、最高のパフォーマンスを引き出し、人間関係の改善にもつなげ、豊かで幸せな人生を築くことを目指しています。
福田ゴンベイ式気功メソッドの特徴
独自の施術法 〜多彩な技術の融合〜
福田ゴンベイ式気功整体は、以下の技術を融合した独自の施術法です。
- 武道の圧法と体重のかけ方
- 台湾官足法(足裏を中心とした反射療法)
- タイ古式マッサージ(筋膜リリースやストレッチ)
- 気功のメソッド(エネルギーの調整)
気の流れを整え、自然治癒力を高める
施術では、筋肉の緊張をやわらげ、血流やリンパの流れを促すような手技を行います。施術後には「身体が軽く感じる」「リラックスできる」といったお声を多くいただいております。
その結果、「冷えが和らいだ」「肩や頭の重さが軽くなった」と感じられる方もいらっしゃいます。
施術の流れ 〜受ける方に合わせたアプローチ〜
施術では、受ける方の状態に応じて、最適な角度・高さ・姿勢で施術を行い、気を注入しながら呼吸に合わせて施術を進めます。特に、足の経絡や静脈を柔らかくほぐし、全身の気の流れを整えることを重視しています。
武道において、急所と経絡は重なる部分が多いため、適切な角度や強さを調整しながら施術を行うのも、このメソッドの特徴です。また、通常の整体のように「受ける側が施術しやすい姿勢を取る」のではなく、施術者が技を駆使して受ける方を自然に動かし、最適な施術の体勢を作るという点も独特なポイントです。
癒しだけではない、身体と心の一体感
福田ゴンベイ式気功整体は、従来のリラクゼーション整体やリフレクソロジーとは異なり、施術リズムとの一体感を大切にし、受ける方が深い安心感を得られるように設計されています。この安心感が、より高い施術効果へとつながるのです。
世界のセレブを虜にするゴンベイ氣功整体
整体術の魅力は、言葉の壁が無い所にもあります。
例え言葉が通じない異国にいたとしても、整体スキルは関係なく相手に癒しを与える事ができます。


写真は世界の大富豪ロバートアレンさんにお会いした際の施術を行った時の写真です。ゴンベイ氣功整体を非常に関心頂き、喜んでいただきました。


整体スキルは癒しのスキルとしては勿論ですが、言葉の壁をこえ、世界共通のコミュニケーションツールとしても非常に効果的なツールです。
福田ゴンベイ式気功整体の広がり
このメソッドは、医師・整体師・セラピストなど健康分野のプロフェッショナルから、一般の方々まで、多くの支持を得ています。日々、体験者や実践者が増え、その効果の広がりを実感しています。
学びの機会と普及活動
現在、福田ゴンベイ式気功整体の価値をより多くの方に知っていただくために、以下のような活動を行っています。
- Webサイト・YouTubeでの情報発信
- オンライン教材の提供(遠方の方でも学べる仕組み)
- 健康お手入れ会やセミナーの開催(直接体験できる場)
- 施術サービスの提供(対面での施術体験)




またネットラジオへ出演させて頂いたり雑誌のSPAで取材をして頂いたりと各種メディアでの発信などもさせて頂いております。

また、福田ゴンベイ式気功整体メソッドを自分で学び・実践したい方のために、オンライン学習教材や合宿形式での技術習得プログラムなど、さまざまな学びの機会も用意しています。